UP
衛生委員会とは?テーマ選定のコツや安全委員会との違いについて

職場における従業員の安全と健康を守ることは、企業の重要な責務です。その中で重要視されるのが「衛生委員会」や「安全委員会」の設置と運営です。
しかし、「衛生委員会と安全委員会ってどう違うの?」「うちはどちらを設置すればいいの?」「それぞれの役割は何?」といった疑問をお持ちの担当者の方もいらっしゃるかもしれません。特に最近では「メンタルヘルスや健康経営」の重要性が広がってきており、関連委員会のあり方や運営方法を見直す企業も少なくありません。
本コラムでは、これらの疑問を解消し、衛生委員会の内容を深堀りしつつ、両者の違い、設置基準、効果的な運営方法、そして月次のテーマ選定のコツまでを詳しく解説します。
【関連サービス】産業医With
【関連サービス】
衛生委員会とは

衛生委員会は、労働者の健康障害の防止、健康の保持増進に関する重要事項について、労使が協力して調査審議、方針を決める場です。
■設置基準・義務
衛生委員会の設置義務があるのは、労働安全衛生法第18条、及び第19条により常時使用する労働者が50人以上の事業場と定められています。これは業種を問わず全ての事業場に適用されます。なお、別途「安全委員会」の設置義務がある事業場は「安全衛生委員会」を設置すれば、別途安全委員会を設置する必要はありません。安全衛生委員会が安全委員会の役割も兼ねるためです。
■審議内容 厚生労働省「職場のあんぜんガイド」より
衛生委員会で審議される内容は、主に労働者の「衛生」に関する事項に限定されます。(詳細は労働安全衛生法第18条)
- 健康診断の実施と結果に基づく対策
- 長時間労働者への対応、面接指導
- メンタルヘルス対策、ストレスチェック制度に関する事項
- 作業環境測定の結果と改善策
- 受動喫煙防止対策
- 感染症予防対策
- 健康増進活動(健康経営)の企画・実施
■委員の構成
衛生委員会は、以下の委員によって構成されます。委員の半数は労働者側から指名された者でなければなりません。
- 委員長 総括安全衛生管理者、または事業の実施を統括管理する者(またはこれに準ずる者)衛生管理者
- 産業医
- 衛生管理者 事業者が指名した者
- 衛生に関する経験を有する労働者(労働者側の推薦が必要)
■開催頻度
原則として、毎月1回以上開催することが義務付けられています。
安全委員会とは

安全委員会は、労働者の危険の防止、労働災害の防止に関する重要事項について、労使が協力して調査審議し、意見を述べる場です。
■設置基準・義務
具体的な設置基準は以下の通りです。
- 常時使用する労働者が50人以上の事業場で、以下の業種:
- 林業、鉱業、建設業、運送業
- 製造業(一部:木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、電気機械器具製造業など)
- 電気業、ガス業、熱供給業、水道業
- 清掃業
- 常時使用する労働者が100人以上の事業場で、上記以外の製造業、電気通信業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、建物サービス業など。
このように、安全委員会の設置義務は、労働災害発生リスクが高いと判断される業種に特化しています。
■審議内容 厚生労働省「職場のあんぜんガイド」より
安全委員会で審議される内容は、主に労働者の「安全」に関する事項に限定されます。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 労働災害の防止対策、危険箇所の改善
- 機械設備や作業方法の安全性の確保、改善
- 安全教育の実施計画とその評価
- 労働災害発生時の原因調査と再発防止策の検討
- 危険性評価(リスクアセスメント)の実施とその結果に基づく対策
- 緊急時の対応計画(防災、避難訓練など)
- 労働者の意見や要望の聴取(安全面に関するもの)
■委員の構成
全委員会の構成員は次のとおりとなります。なお、[1]の委員は1人となります(詳細は労働安全衛生法第17条第2項から第5項)。
[1]総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
[2]安全管理者のうちから事業者が指名した者
[3]当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
※[1]の委員は、安全委員会の議長を務めます。
■開催頻度
原則として、毎月1回以上開催することが義務付けられています。
両者の違い

両委員会の主な違いを以下の表にまとめました。
|
項目 |
衛生委員会 |
安全委員会 |
|
設置目的 |
労働者の健康障害の防止、健康の保持増進 |
労働者の危険の防止、労働災害の防止 |
|
設置義務 |
- 常時50人以上(全業種) |
- 常時50人以上かつ特定の労働災害リスクが高い業種 |
|
- 常時100人以上かつ特定の業種 |
||
|
審議内容 |
労働者の心身の「健康」と「衛生」に関する事項 |
労働者の「安全」に関する事項、労働災害防止 |
|
必須委員 |
衛生管理者、産業医が必須 |
安全管理者が必須(産業医は必須ではない) |
|
設置関係 |
安全衛生委員会を設置すれば別途設置不要 |
安全衛生委員会を設置すれば別途設置不要 |
このように、衛生委員会が「健康」に、安全委員会が「安全」に特化している点が最も大きな違いです。どちらの委員会も、企業が従業員にとって安全で健康な職場環境を提供するための重要な役割を担っています。自社の業種と従業員数を踏まえ、適切に委員会を設置・運営することが求められます。
衛生委員会の設置から開催までの流れ

委員会を効果的に運営するためには、適切な準備と手順を踏むことが重要です。
■委員(関係者)の選任
まず、衛生委員会の構成員を適切に選出します。労働安全衛生法に基づき、以下の委員で構成されます。特に、労働者側の委員は、現場の意見や健康に関する課題を吸い上げ、委員会に反映させる上で非常に重要な役割を担います。公正かつ適切な方法で選出するようにしましょう。会社によっては従業員代表をメンバーに選任するケースもあります。
■規程の作成
委員会の運営に関するルールを明確にするため、「衛生委員会規程」を作成します。規程には、委員会の目的、委員の構成、開催頻度、議事録の作成・保管、審議事項の決定方法、秘密保持義務などを明記し、委員全員に周知します。
■年間計画の検討・作成
年間を通してどのような健康関連テーマを審議するか、計画を立てることが非常に重要です。季節ごとの健康課題(熱中症、インフルエンザ、花粉症など)、定期健康診断の実施月、ストレスチェックの実施・集団分析報告、法改正、過去の健康相談データ、従業員からの要望などを考慮して、バランスの取れた年間計画を作成しましょう。これにより、行き当たりばったりの運営を避け、計画的かつ継続的な健康管理活動が可能になります。
■委員会の開催
年間計画に基づき、定期的に委員会を開催します。
1 事前準備: 議題の選定、関連資料の準備、委員への案内、出席確認を行います。議題は事前に委員に共有し、意見を募ることで、より実りのある議論が期待できます。
2 議事進行: 議長が円滑な議事進行を心がけ、全ての委員が意見を述べやすい雰囲気を作ります。産業医や衛生管理者の専門的な知見を積極的に活用しましょう。
3 議論と決定: 提出された議題について議論を行い、必要な事項については決議します。
4 議事録作成: 審議内容、意見、決定事項などを明確に記録し、委員全員に共有します。議事録は事業場内に掲示するなどして、労働者へも周知することが労働安全衛生法で義務付けられています。
5 改善策の実行と確認: 委員会で決定した改善策は、確実に実行に移し、次回の委員会でその効果や進捗を確認します。
月次のテーマをどう選ぶか?

衛生委員会の効果を最大化するためには、毎月取り上げるテーマが重要です。マンネリ化を防ぎ、従業員の関心を引きつけるテーマを選定しましょう。
■テーマの決め方
- 年間計画に基づいた選定: あらかじめ定めた年間計画の中から、その月に最適なテーマを選びます。この年間計画には、ストレスチェックの実施月や、定期健康診断のフォローアップ、特定の時期に増加しやすいメンタルヘルスの課題(例:新生活による適応障害、夏季・冬季うつなど)を盛り込んでおくことが効果的です。
- 季節性や行事を考慮: 季節特有の心身の不調(花粉症、梅雨時の気象病、夏の疲労蓄積、冬季の気分変動など)や、年度末・年度初めの繁忙期、人事異動期、長期休暇前後など、特定の時期に生じやすいストレス要因をテーマにします。
- 社内の実態・課題から選定
- 健康診断の結果: 定期健康診断や特殊健康診断の結果から、従業員の健康状態の傾向や、特に注意が必要な健康課題を把握し、対策を検討します。
- ストレスチェックの集団分析結果: 部署ごとのストレス傾向、職場環境要因を詳細に分析し、喫緊の課題や改善が必要な点をテーマとします。
- 産業医や保健師からの情報: 面談や健康相談を通じて把握された従業員の傾向、頻発する健康課題(不眠、不安、疲労感など)を参考にします。
- 従業員アンケートや意見箱: 匿名での意見収集やアンケート結果から、従業員が実際に抱えているストレス要因や不満を把握します。
- 休職・復職者の状況: メンタルヘルス不調による休職・復職者の発生状況や傾向を分析し、予防やサポート体制強化の視点を取り入れます。
- 作業環境測定結果: 騒音、照明、温度、化学物質などの測定結果に基づき、作業環境改善の必要性を検討します。
- 法改正や行政からの情報: 労働安全衛生法や関連法令の改正(例:パワハラ防止法の義務化)、厚生労働省からのメンタルヘルス対策や健康増進に関する最新情報などをキャッチアップし、必要な対策を審議します。
- 過去のテーマの振り返り: 過去に実施した健康対策の効果検証や、未解決の課題について再度取り上げ、継続的な改善を図ります。
毎月のテーマ例

具体的なテーマ例を挙げます。これらを参考に、貴社の実情に合わせて選定・調整してください。
1月: 冬季の健康管理(感染症対策、冷え対策)、年末年始の疲労回復、生活習慣病予防
2月: 腰痛・肩こり対策(VDT作業を含む)、花粉症対策、乾燥対策と保湿
3月: 年度末・年度初めのメンタルヘルスケア(異動・新生活ストレス対策)、健康診断後の生活習慣改善勧奨
4月: 新入社員向け健康教育(ストレスマネジメント、健康相談窓口周知)、定期健康診断の実施計画
5月: ストレスチェック結果報告と集団分析に基づく職場環境改善、五月病対策とリフレッシュ推進
6月: 梅雨時期の体調管理(気圧変動による不調対策)、食中毒予防、熱中症予防の呼びかけ開始
7月: 熱中症対策の徹底、夏季の食欲不振・消化器系トラブル対策、冷房病対策
8月: 残暑対策と疲労回復、夏休み明けの心身のリフレッシュ、感染症予防(夏風邪など)
9月: ストレスチェックの実施準備、メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応、運動習慣の促進
10月: インフルエンザ予防接種の推奨、過重労働対策の進捗確認、特定保健指導の推進
11月: 冬季うつ対策と睡眠の質向上、感染症対策の強化、作業環境の改善(換気、加湿など)
12月: 年末の業務負担による健康影響、セルフケアの重要性、健康意識向上に向けた啓発
■(メンタルヘルス寄り)毎月のテーマ例
よりメンタルヘルスを意識した場合のテーマ例もご紹介します。
1月: 休暇明けの心身のリセットと冬季の気分変動対策
2月: 職場コミュニケーションの活性化と心理的安全性向上
3月: 年度末の繁忙期と環境変化に伴うストレスマネジメント
4月: 新入社員・異動者の適応支援と「五月病」の予防
5月: ストレスチェック結果の活用と職場環境改善への具体的なアクション
6月: 梅雨時期の心身の不調対策と自律神経の整え方
7月: 夏季の疲労蓄積とメンタルヘルス、夏休み前のリフレッシュ
8月: 夏季休暇明けの心身の切り替えとモチベーション維持
9月: メンタルヘルス不調の早期発見と相談の促進
10月: 過重労働対策とワークライフバランスの見直し
11月: ハラスメント対策と多様性を尊重する職場づくり
12月: 年末の業務負担増とセルフケア
ストレスチェックとの関連

ストレスチェックの結果は、衛生委員会(または安全衛生委員会)にとって非常に重要な審議事項となります。
- ストレスチェック結果の報告: 全体的な実施状況や受検率、高ストレス者の状況などが報告されます。
- 集団分析結果の活用: 部署ごとのストレス傾向や職場環境要因が分析され、衛生委員会でその結果が共有されます。
- 職場環境改善の検討: 集団分析の結果を踏まえ、どのような職場環境改善策が効果的か、委員会で具体的な対策を議論し、実行に移します。
- 高ストレス者への対応: 面接指導の勧奨や、必要に応じて就業上の配慮についても議論されることがあります。
ストレスチェックの結果を単に「実施しただけ」で終わらせず、衛生委員会で深く議論し、具体的な職場環境改善へとつなげることで、従業員のメンタルヘルス不調の未然防止と、より健全な職場づくりが実現できます。


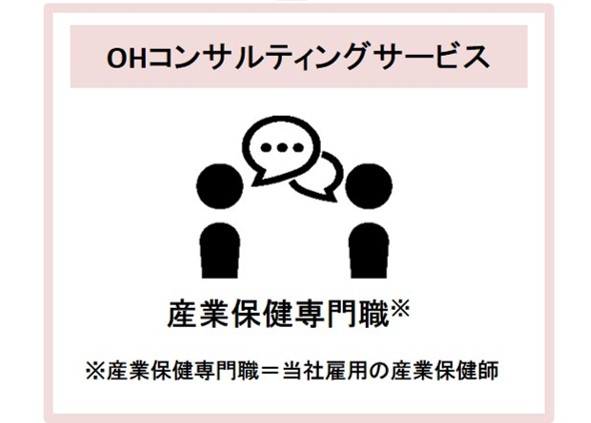 産業保健体制に関わる活動計画・体制構築・運用に関するコンサルティング
産業保健体制に関わる活動計画・体制構築・運用に関するコンサルティング