UP
ストレスチェックが50名未満の事業場も義務化 知るべきポイント
目次
【関連サービス】詳細はこちら
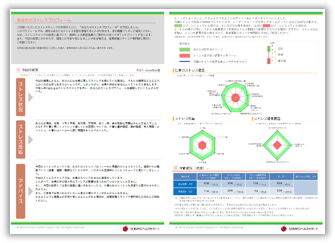 ストレスチェック「LLax seed」
ストレスチェック「LLax seed」
法定範囲に対応できるサービスはもちろん、努力義務となっている集団分析、職場環境改善や高ストレス者の対応など、幅広いサービスメニューをご用意しています。

現在、従業員数50名以上の事業場に義務付けられているストレスチェック制度ですが、労働安全衛生法の改正により、その対象が50名未満の事業場にも拡大される見通しとなりました。
本記事では、この法改正の概要から、企業への具体的な影響、そして初めてストレスチェックを実施する企業が知っておくべきポイントを、深掘りしてお伝えします。
公布後3年以内に施行。労働安全衛生法の改正内容とは
現行の労働安全衛生法では、常時使用する労働者が50人以上の事業場に対し、年1回のストレスチェック実施が義務付けられています。これは2015年12月に施行されたもので、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止し、早期発見・早期対応に繋げることを目的としています。
その後、2024年2月に厚生労働省の労働政策審議会は、ストレスチェック制度の対象を常時使用する労働者が50人未満の事業場にも拡大することを盛り込んだ労働安全衛生法の改正案を了承しました。この改正は、公布後3年以内に施行される予定です。
この背景には、中小企業におけるメンタルヘルス不調者の増加や、大企業との健康格差の是正といった課題があります。従業員の健康は企業の最も重要な財産であるという認識が社会全体で高まる中、規模に関わらず全ての労働者が安心して働ける環境を整備する必要があるとの判断が下された形です。
今後、公布の動向や施行時期については引き続き注視が必要ですが、対象となりそうな場合は、今から準備を始めることが賢明と言えるでしょう。
今までの50人未満事業場の実施傾向は?

では、これまで50人未満の事業場では、ストレスチェックはどの程度実施されてきたのでしょうか。厚生労働省のデータによると、従業員数10~49人規模の事業場では実施率は58%少々にとどまっています。一方、元々義務化の対象である50名以上の事業場では実施率は90%近くとなっています。(厚生労働省「令和6年労働安全衛生調査」)
50人未満は義務ではないため、コストや工数の点からもストレスチェックを実施しない判断をされるのも無理はないかと思います。
企業への影響① 小規模事業場を抱えている企業
まず、企業内に従業員数50名未満の事業場(店舗、支店、営業所など)を抱えている企業について考えてみましょう。
これまで、本社や一部の大規模事業場ではストレスチェックを実施していても、小規模な事業場では対象外としていたケースがあったはずです。しかし義務化後は、これらの小規模事業場も本社と同様にストレスチェックを実施し、適切に運用していく必要があります。
これは、企業全体のメンタルヘルス対策の均質化を意味します。本社の人事部門や産業保健スタッフは、企業全体の体制構築、運用の標準化、そして各事業場への情報提供やサポート体制の強化が求められるでしょう。特に、これまで関与が少なかった小規模事業場では、新たな制度導入に対する戸惑いや負担感が生じやすいため、きめ細やかなフォローアップが不可欠です。
コスト面でも、これまで以上にグループ全体での予算確保や、効率的な外部サービスの活用などを検討する必要が出てくるでしょう。
企業への影響② 従業員数50名未満の企業
次に、従業員数50名未満の企業、いわゆる中小企業にとっての影響です。多くの企業にとって、ストレスチェック制度は「初めての経験」となるでしょう。
これまでメンタルヘルス対策に十分なリソースを割けていなかった企業にとって、ストレスチェックの義務化は、確かに新たな業務負担となるかもしれません。人事担当者がいない、労務管理の専任者がいない、産業医との契約がないといった企業も少なくないでしょう。
しかし、これは企業が従業員の健康を守る責任を再認識し、より働きやすい職場環境を構築する絶好の機会と捉えることもできます。ストレスチェックは、単なる義務の履行に留まらず、職場の現状を客観的に把握し、生産性向上や離職率低下に繋げるための有効なきっかけとなり得ます。
準備不足のまま法施行となり、あわてて実施をするよりは、施行前に一度実施をしておくことで、予期せぬトラブルや課題点を洗い出しておくと良いでしょう。
前倒し実施をする場合のポイント

法施行前であれば、あくまでも企業は任意でストレスチェックを実施する扱いになるため、現行法で決められている通りに行う必要はありません。(同じように行えるのであればそれがベストです)
例えば、高ストレス者が出た場合に、面接勧奨まで行うのかどうかや、実施者を選任しないなどのアレンジは可能です。注意点としては、ストレスチェック制度に則る必要はないですが、個人情報保護法などは順守する必要があるということです。ストレスチェックの個人結果の取り扱いや結果閲覧者、利用目的などについてはしっかりと明示し、従業員の同意を得たうえで実施をする必要があります。
初めてストレスチェックをする企業が知るべきポイント

ここでは現行法がそのままの内容で50人未満の事業場に適用されたとしてご説明いたします。
■実施体制
ストレスチェック制度では、「実施者」「実施事務従事者」「面接指導を行う医師」など、役割分担が明確に定められています。
実施者
医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士など、専門的な知識を持つ者が担当します。
実施事務従事者
実施者の指示のもと、事務的な作業を行います。ストレスチェック結果に触れることになるので、人事権がある方を選任することはできません。
多くの小規模事業場では、社内に実施者となり得る人材がいないケースが多いため、外部の産業医や保健師、または専門機関に委託することを検討するのが現実的です。
■利用するストレスチェック
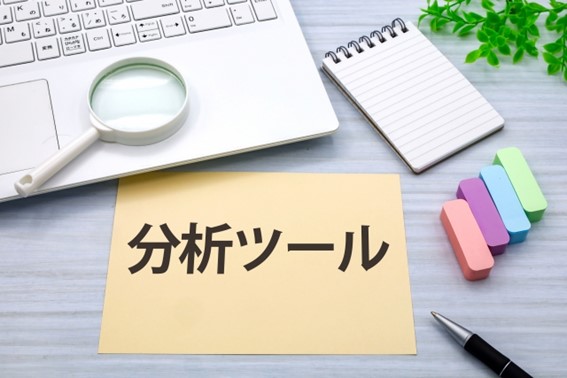
ストレスチェックの質問項目は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を基本とします。これは無料で利用できますが、民間サービスによってはより詳細な分析や、職場環境改善に繋がるアドバイスを提供してくれるものもあります。企業のニーズや予算に応じて選択しましょう。
それ以外に、エンゲージメント尺度を盛り込んだ「新職業性ストレス簡易調査票(80項目)」を利用する企業も増えてきています。
参考サイト:厚生労働省「こころの耳」
■高ストレス者への対応
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者に対しては、本人の希望に基づき、医師による面接指導を勧奨する義務があります。面接指導の結果、医師が必要と判断した場合は、就業場所の変更や残業時間の制限など、会社として適切な就業上の措置を講じる必要があります。このプロセスは、個人のプライバシー保護に最大限配慮しながら進めることが重要です。
■各種情報の取り扱い
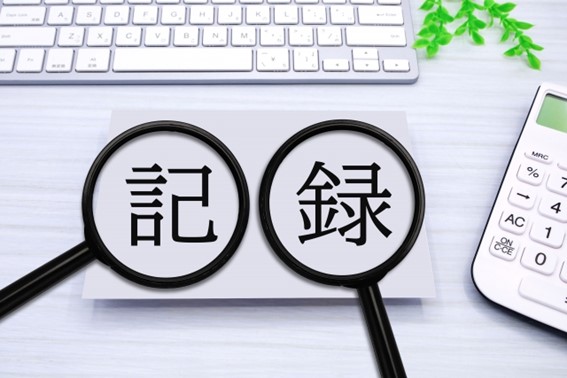
ストレスチェックの結果は、個人のデリケートな健康情報であり、厳重な管理が求められます。
・事業者は、個人の同意なく結果を会社が把握することはできません。
・同意を得て会社が結果を把握した場合でも、その情報を不利益な取り扱いに利用することは固く禁じられています。
・ストレスチェックの結果は、原則として5年間保存する必要があります。
■ストレスチェック結果の活用
ストレスチェックは、単に個人のストレスレベルを測るだけでなく、集団分析を行うことで、職場のストレス状況や課題を浮き彫りにする重要なツールです。部署やチームごとのストレス傾向を分析し、ハラスメント対策、業務負荷の適正化、コミュニケーション改善など、具体的な職場環境改善活動に繋げていきましょう。義務だから行う、ではなく「より良い職場づくり」のための投資だと考え、積極的に活用することが成功の鍵です。
外部委託をしたほうがよいケース

初めてストレスチェックを実施する企業や、社内リソースが限られている企業にとって、外部委託は非常に有効な選択肢です。
専門知識・ノウハウが不足している
ストレスチェック制度は専門性が高く、法的な要件も複雑です。専門機関に委託することで、法令遵守はもちろん、高ストレス者への適切な対応や、集団分析結果の活用方法など、質の高いサポートが期待できます。
公平性・中立性を確保したい
社内で実施すると、従業員が「会社に結果を知られるのではないか」と不安を感じ、正直な回答をためらう可能性があります。外部機関が間に入ることで、公平性・中立性が担保され、従業員も安心して受診しやすくなります。
人事・労務担当者の負担を軽減したい
制度設計から実施、結果の管理、面接指導の調整など、ストレスチェックには多くの業務が発生します。外部委託することで、これらの事務負担を大幅に削減し、担当者は本来の業務に集中できます。
産業医や保健師がいない・不足している
実施者や面接指導医の確保が難しい場合、外部委託サービスで一括して手配してもらうのが効率的です。
内製化したほうがよいケース

一方で、企業の状況によっては、内製化を検討するメリットもあります。
コストを抑えたい
外部委託費用は、従業員数に応じて発生します。自社で実施体制を構築できれば、長期的に見てコスト削減に繋がる可能性があります。
社内に専門家がいる
産業医や保健師、専門研修を修了した看護師などが社内にいる場合、内製化のハードルはぐっと下がります。
既存の産業保健体制と連携させたい
産業保健体制を構築しており、産業医などが日頃から従業員の健康状態を把握している場合、ストレスチェックもその一環として内製化することで、より統合的なメンタルヘルス対策が可能になります。
柔軟な運用をしたい
自社独自の質問項目を追加したい、急いで実施したいなど、柔軟な運用を求める場合は内製化が有利です。
ただし、内製化する場合でも、法令遵守、個人情報保護、そして実施者の専門性確保は必須です。これらの条件を満たすことが難しい場合は、無理に内製化せず、専門家のサポートを得ることを強くお勧めします。
まとめ
従業員50名未満の事業場にも、ストレスチェックの義務化が拡大される見通しです。2024年2月の労働政策審議会で承認され、労働安全衛生法の改正により公布後3年以内に施行される予定です。中小企業におけるメンタルヘルス不調の増加や健康格差是正が背景にあり、これまで実施率が低かった企業や、グループ内の小規模事業場への影響は大きいでしょう。
初めて実施する企業は、医師や保健師等の「実施者」選任、高ストレス者への面接指導勧奨、個人情報の厳重な取り扱い、そして集団分析結果を活かした職場環境改善が重要なポイントとなります。義務化を機に、企業は従業員の健康を守る責任を再認識し、働きやすい環境整備を考える必要があります。
実施方法は、専門性や公平性確保、担当者の負担軽減を重視するなら外部委託が有効です。社内に専門家がいてコストを抑えたい、柔軟な運用を求める場合は内製化も可能ですが、法令遵守と個人情報保護は必須です。
この義務化を、単なる負担ではなく、従業員のエンゲージメント向上や企業成長に繋がる好機と捉え、今から適切な準備を始めることが賢明です。
【関連サービス】詳細はこちら
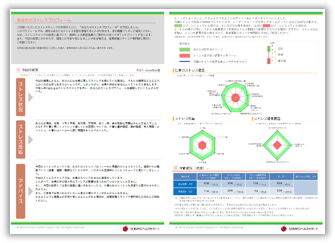 ストレスチェック「LLax seed」
ストレスチェック「LLax seed」
法定範囲に対応できるサービスはもちろん、努力義務となっている集団分析、職場環境改善や高ストレス者の対応など、幅広いサービスメニューをご用意しています。
