UP
健康経営は「意味がない」のか?企業が知るべきメリット・デメリットと成功の秘訣
目次
なぜ今、「健康経営」なのか?
※ 「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
日本の企業を取り巻く環境は、目まぐるしく変化しています。
少子高齢化による人口減少、働き方の多様化、そして予測不能な時代を意味する「VUCA」といったキーワードが示すように、企業はかつてないほどのスピードで変革を求められています。
そんな中で、多くの経営者や人事担当者が注目しているのが「健康経営」です。
「健康経営」と聞くと、単なる福利厚生の一環、あるいは従業員の健康診断を充実させることだと捉える方もいるかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。
健康経営は、もはや企業の経営戦略において欠かせない重要な柱となっています。従業員の健康を経営的な視点から考え、戦略的に実践することで、企業の持続的な成長や生産性向上に繋げようというアプローチです。
「本当に効果があるの?」「うちの会社には関係ないんじゃ?」――そんな疑問を抱く方もいるでしょう。特に、社内で「健康経営優良法人の認定って意味あるの?」と言われたら、取り組むことに二の足を踏んでしまうかもしれません。
本記事では、そうした疑問に真っ向から答え、健康経営の価値をご説明します。
健康経営が企業にもたらす「確かなメリット」だけでなく、導入時に直面する可能性のある「デメリット」や「課題」、そしてそれらをどのように乗り越えて「意味あるもの」にするか、具体的な成功の秘訣までを徹底解説します。
健康経営に取り組む「確かなメリット」:投資対効果を生む5つの恩恵

健康経営は、単なるコストではなく、企業が未来へ成長するための「投資」です。その投資がもたらす具体的な恩恵を見ていきましょう。
①生産性・エンゲージメントの向上
従業員が心身ともに健康であれば、そのパフォーマンスは劇的に向上します。
集中力が高まり、クリエイティブな発想が生まれやすくなるだけでなく、欠勤(アブセンティーイズム)や、体調不良による業務効率の低下(プレゼンティーイズム)も改善されます。
実際に、健康経営に取り組む企業では、残業時間の削減や離職率の改善といった目に見える効果が報告されています。
健康な従業員は、仕事へのモチベーションも高く、企業へのエンゲージメント(愛着心や貢献意欲)も自然と高まるのです。
②企業イメージ・採用競争力の強化
「従業員を大切にする企業」という評判は、企業のブランドイメージを大きく向上させます。
これは、顧客や取引先からの評価だけでなく、優秀な人材の獲得にも直結します。求職者は、給与だけでなく、働きがいや働きやすさといった「企業の魅力」を重視する傾向にあります。
健康経営は、そうした企業の魅力を対外的にアピールする強力なツールとなり、採用競争力を高めます。
また、昨今注目されるESG投資(環境・社会・ガバナンスへの配慮を重視する投資)においても、従業員の健康への取り組みは重要な評価ポイントです。
③医療費・休職コストの削減
従業員が健康であれば、企業が負担する医療費や、休職者が発生した場合の代替人員コスト、そしてその間の業務停滞といった間接的なコストを大幅に抑制できます。
健康診断の徹底や予防医療への投資は、一見費用がかかるように見えますが、長期的に見れば疾病の重症化を防ぎ、結果的に医療費の増加を抑えることに繋がります。
健康な従業員が増えれば、病欠や休職が減り、安定した事業運営が可能になります。
④ リスクマネジメントの強化とBCP対策
現代社会では、メンタルヘルス不調や生活習慣病によるリスクは無視できません。健康経営は、これらのリスクを低減するための予防策として機能します。
早期発見・早期対応の体制を整えることで、従業員の健康悪化による企業活動への影響を最小限に抑えます。
さらに、健康な従業員が多い企業は有事の際にも回復力が高く、事業継続計画(BCP)の観点からも強固であると言えます。
⑤組織活性化とイノベーション促進
健康経営は、従業員同士のコミュニケーションを活発化させ、職場の一体感を醸成します。健康を意識した施策や社内イベントの提供は、部署間の垣根を越えた交流を生み、新たな協力関係を築くきっかけにもなります。
心身ともに健康な状態は、従業員の好奇心やチャレンジ精神を刺激し、ひいては企業全体のイノベーションを生み出す土壌となるでしょう。
「健康経営優良法人なんて意味ない」は本当か?デメリットと課題の乗り越え方

「健康経営は重要だと言うけれど、実際にはデメリットもあるんでしょ?」「健康経営優良法人なんて、形だけで意味がないって聞くけど…」
ここでは、そうした声にお応えして、健康経営に潜む課題や、よくある誤解について掘り下げてみましょう。
①健康経営の「デメリット」として挙げられる点
まず、健康経営の導入・運用には、確かにいくつかの「デメリット」が存在します。
- 導入・運用コストの発生: 健康診断の充実、保健師や産業医との契約、施設の整備、健康管理システムの導入など、本格的に取り組むほど初期投資や継続的な費用がかかることは避けられません。
特に今までそういった予算をとってこなかった企業にとっては、これらの費用が負担に感じられるかもしれません。 - 効果測定の難しさ・時間的要因: 従業員の健康状態が劇的に改善したり、生産性が目に見えて向上したりするまでには、ある程度の時間が必要です。
短期的な成果が出にくいことから、投資に対する費用対効果が見えにくく、途中で諦めてしまうケースも少なくありません。 - 従業員の理解・協力不足: 健康に対する意識や取り組み方は人それぞれです。
中には、企業からの健康介入を「お節介」と感じたり、個人のプライバシーに踏み込まれることに抵抗を感じたりする従業員もいるでしょう。
トップダウンの施策だけでは、なかなか浸透しないこともあります。
②「意味のない健康経営」になりかねない?背景と実態
そして、「意味がない」という疑念が生まれる背景には、以下のような陥りうる実態があると考えられます。
- 認定取得が目的化してしまうケース: 健康経営優良法人に認定されること自体がゴールとなってしまい、形式的な取り組みに終始してしまう企業が存在します。
認定マークの取得が先行し、従業員の健康増進や生産性向上という本来の目的から逸脱してしまうと、確かに「意味がない」と感じられても仕方ありません。 - 形だけの運用に陥ることで、真のメリットを享受できていない: 例えば、単に健康診断を実施するだけで、その結果に基づいた具体的なフォローアップや改善策が講じられないケース。
あるいは、従業員のニーズを把握せず、企業側が一方的に提供する施策が、実はあまり活用されていないケースなどです。
こうした「やらされ感」のある取り組みでは、従業員のエンゲージメントは高まりませんし、費用対効果も期待できません。 - 企業規模や業種に合わない施策導入によるミスマッチ: 大企業で成功した施策が、そのまま中小企業に当てはまるとは限りません。
自社の従業員の年齢層、業務内容、企業文化などを考慮せず、表面的な取り組みだけを真似しても、効果は薄いでしょう。
③これらの課題を乗り越えるための視点
しかし、これらのデメリットや課題は、決して乗り越えられないものではありません。重要なのは、健康経営を「費用」と捉えるのではなく、「未来への投資」と捉える長期的な視点を持つことです。
コストについては、投資対効果を見極め、費用のかかる施策だけでなく、従業員同士でできる運動機会の提供など、身近で手軽なことから始める「スモールスタート」も有効です。
効果測定は、短期的な成果だけでなく、長期的な視点でのKPI(重要業績評価指標)を設定し、PDCAサイクルを回しながら地道に進めることが重要です。
そして、従業員とのエンゲージメントを高めるためには、一方的な施策の押し付けではなく、彼らの声に耳を傾け、「共につくっていく」意識で取り組むことが不可欠です。
「健康経営優良法人」認定も、取得自体を目的とするのではなく、あくまで企業の健康経営推進を促進するための「手段」と捉え、認定後の継続的な改善と進化を目指すことが、真に「意味あるもの」にするための鍵となるのです。
成功へのロードマップ:健康経営を「意味あるもの」にする具体的なポイント

では、これらのデメリットを乗り越え、健康経営を成功に導くためには、具体的にどのような点を意識すれば良いのでしょうか。
①経営トップの強いコミットメント
健康経営を成功させる上で、最も重要なのが経営層の強いコミットメントです。経営トップ自らが健康経営の重要性を理解し、率先して健康増進に取り組む姿勢を示すことで、従業員全体の意識を変えることができます。
健康経営を単なる人事・総務の担当業務に留めず、経営戦略の柱と位置づけ、明確なビジョンを社内外に発信することで、従業員も安心して取り組みに参加できるようになります。
②従業員との対話と「共創」
健康経営で成功している企業は、従業員のニーズを丁寧に把握し、彼らの意見を積極的に取り入れています。
アンケートやヒアリングを通じて、どんな健康課題に悩んでいるのか、どんなサポートを求めているのかを理解することが第一歩です。
そして、企業側が一方的に施策を提供するのではなく、従業員も企画段階から参加できるような「共創」の機会を設けることで、主体的な参加を促し、施策への満足度を高めることができます。
小さな成功体験を積み重ね、参加したくなるようなインセンティブを設けるのも効果的です。
③費用対効果を意識した「段階的アプローチ」
全ての施策を一度に導入する必要はありません。まずは、自社の現状や従業員のニーズに合った、費用対効果の高い施策からスモールスタートしましょう。
例えば、従業員食堂での健康メニュー提供、ウォーキングイベントの開催、ストレスチェック後のカウンセリング体制強化など、手軽に始められるものから着手し、その効果を検証します。
成功事例を積み重ねながら、徐々に施策の範囲を広げ、投資額を増やしていく「段階的アプローチ」が、無理なく健康経営を定着させる秘訣です。
④外部リソースの賢い活用
自社だけで全てをまかなう必要はありません。産業医や保健師、健康経営コンサルタントといった専門家の知見を借りることは、非常に有効です。
こうした専門家は、個別の健康課題に対する専門的なアドバイスや、法的な要件への対応、効果的な施策の提案など、多岐にわたるサポートを提供してくれます。
また、健康管理システムやオンラインフィットネスサービスなどのITツールを導入することで、健康データの管理を効率化したり、従業員の健康増進活動をサポートしたりすることも可能です。
⑤「健康経営優良法人」認定を「目的」ではなく「手段」として捉える
「健康経営優良法人」の認定は、企業の健康経営への取り組みが一定の基準を満たしていることを示す、非常に有効なブランディングツールです。
しかし、この認定取得自体をゴールにしてしまうと、本来の目的を見失いかねません。
認定は、あくまで「企業として健康経営に取り組むための手段」であり、そのプロセスを通じて従業員の健康増進と企業の成長を実現することが真の目的です。
認定後もPDCAサイクルを回し、継続的に改善と進化を続けていくことが、企業の持続的な発展に繋がります。
関連記事・・・これから健康経営を推進したい企業のために
まとめ:健康経営は「未来への最良の投資」である
ここまで、健康経営が企業にもたらす確かなメリットと、導入時に懸念されるデメリット、そして「健康経営優良法人って意味あるの?」という疑問の背景と、それを乗り越えるための具体的なポイントを解説してきました。
確かに、健康経営には初期投資や効果測定の難しさといった課題があります。
しかし、それらは経営層の強いコミットメント、従業員との共創、段階的なアプローチ、そして外部リソースの活用によって、十分に克服可能です。
そして何よりも、健康経営がもたらす「生産性の向上」「企業イメージの向上」「コスト削減」「リスクマネジメントの強化」「組織の活性化」といったメリットは、デメリットをはるかに上回る価値があります。
従業員の健康を守ることは、単なる人道的な配慮に留まらず、企業の持続的な成長と社会貢献に不可欠な「未来への最良の投資」なのです。
これまでの解説で、健康経営に取り組むことへの前向きな確信を持っていただけたのではないでしょうか。健康経営の一歩が、企業の未来を拓き、従業員と共に発展し進化するためのひとつの鍵となるでしょう。
関連サービス:健康経営推進総合コンサルティング
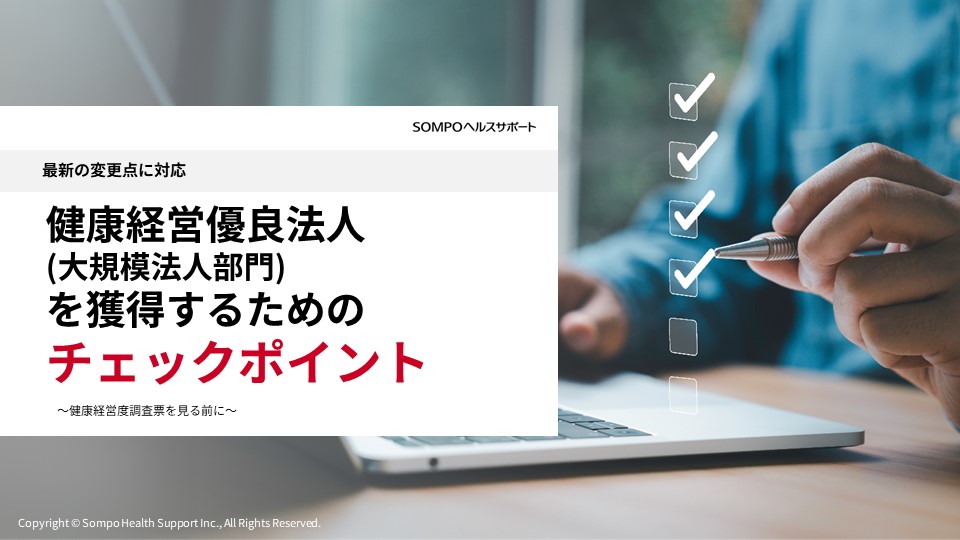 関連資料
関連資料
健康経営優良法人を獲得するためのチェックポイント
・認定基準の全体像
・認定要件大項目ごとのポイントをまとめたガイドです。

