UP
産業医の選任「義務」と「必須業務」を徹底解説!
目次
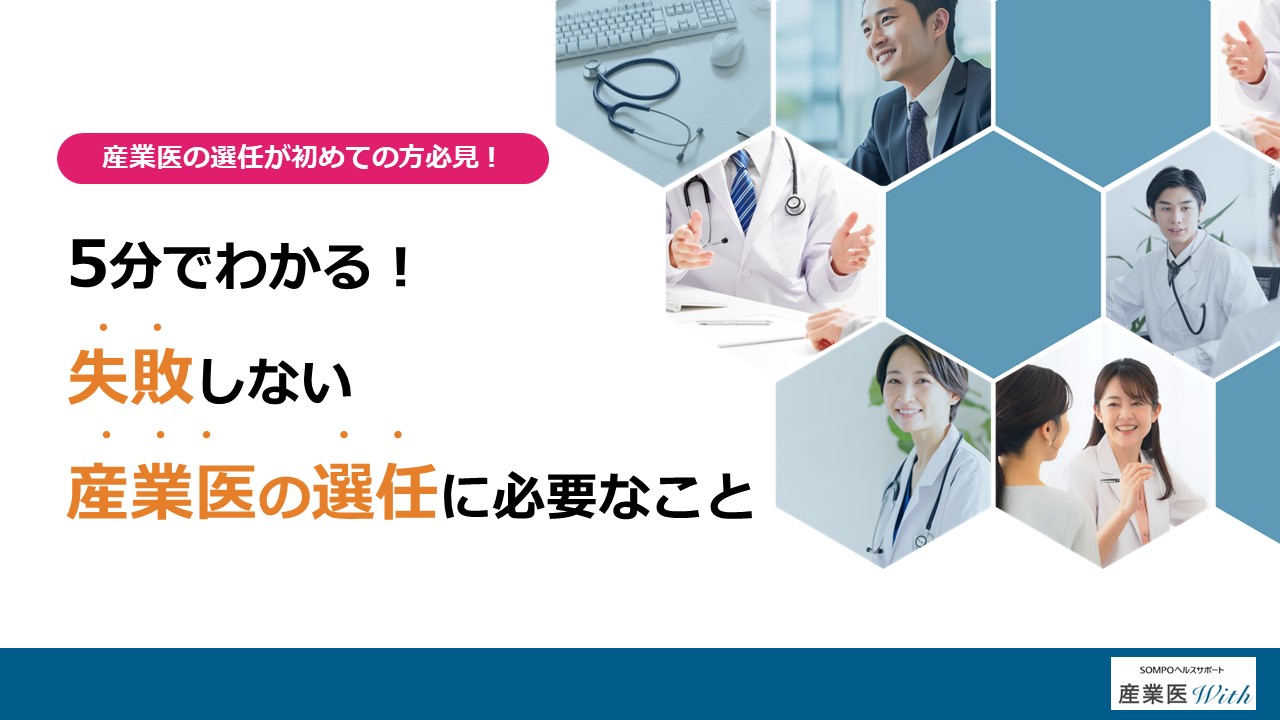 関連資料
関連資料
産業医の選任で注意すべきポイントや
知っておくべき情報を”失敗しない”
観点からまとめたお役立ち資料です。

本記事では、産業医の選任において企業が知っておくべき産業医の法的義務と対応法令、そして推奨業務を解説します。さらに、義務と業務を遂行する適切な産業医の選び方や、選任における注意点、そして産業医を選任しなかった場合の罰則についても詳述します。
「産業医って、何をする人?」「うちは50人以上の事業所になったから、産業医を選任しないといけないらしいけど、何から手をつければいいかわからない」「産業医は選任しているけれど、適切に業務を任せられているか不安」
このような企業の方も、この記事を読んで、産業医制度への理解を深め、最適な産業医を選任するための一歩を踏み出しましょう。
産業医制度の概要と企業が負う義務
■産業医とは?企業が産業医を必要とする理由
産業医とは、事業場において労働者の健康管理などを行う医師のことです。
現代社会では、職場における安全衛生に限らず、従業員の健康障害やメンタルヘルス不調など、人材の健康課題は多様化・複雑化しています。
産業医は、医学的見地から専門知識を活かして企業や労働者に対して指導や助言を行うことにより、企業の健全な運営を支えます。
企業が産業医を必要とする主な理由は、労働者の健康と安全を守る社会的責任と、労働安全衛生法に基づく法的義務の2点に集約されます。
■産業医の法的選任義務と対象事業場
労働安全衛生法により、企業は一定の条件を満たす場合に産業医を選任する義務があります。(※労働安全衛生法 第13条、労働安全衛生法施行令 第4条)
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場:産業医を1人以上選任することが義務付けられています。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または特定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場:専属の産業医を1人以上選任することが義務付けられています
「常時使用する労働者」とは、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトであっても、継続的に使用される労働者を含みます。この人数は、雇用形態ではなく、事業場で働く実態に基づいて判断されます。
産業医の選任は、対象事業場となった日から14日以内に行い、管轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。この義務を怠ると、後述する罰則の対象となる可能性があります。
産業医が法的に「必ず」行うべき業務(法的義務)
ここからは、労働安全衛生法によって産業医が必ず行わなければならないと定められている業務(法的義務)について、対応法令とあわせて詳しく見ていきましょう。これらの業務は、企業が法令を遵守し、労働者の安全と健康を確保するために不可欠なものです。(※労働安全衛生法 第13条第3項、労働安全衛生規則 第14条)
■健康診断の実施と管理、事後措置への意見
産業医の主要な義務業務の一つが、健康診断に関わることです。
- 健康診断の計画、実施、結果の確認:企業が実施する定期健康診断、特殊健康診断などの計画段階から関与し、適切に実施されているかを確認します。
- 健康診断結果に基づく事後措置への意見:健康診断の結果、異常があった労働者に対して、就業上の措置(労働時間の短縮、配置転換など)や保健指導が必要と判断された場合、事業者に対して医学的な意見を述べます。これは、労働者の健康状態に応じた適切な就業環境を確保するために非常に重要です。
- 面接指導の実施:健康診断の結果、医師が必要と認めた労働者や、労働者からの申し出があった場合に、面接指導を行います。
■ 職場巡視による職場環境の評価と改善
職場巡視は、産業医が義務として月に1回以上(または、事業者と産業医の同意があれば2ヶ月に1回以上)行わなければならない業務です。(※労働安全衛生規則 第15条第1項)
- 作業環境の確認:工場やオフィスなど、実際に労働者が働く場所を巡視し、作業方法や衛生状態、労働者の行動などに危険がないか、有害な環境になっていないかを確認します。
- 施設・設備の確認:休憩室、食堂、更衣室、トイレなどの衛生設備が適切に管理されているかを確認します。
- 作業員の健康状況の把握:巡視中に労働者とコミュニケーションを取り、健康状態や職場に対する意見などを聞くこともあります。
- 改善点の指摘と助言:巡視で問題点を発見した場合、事業者に対して改善のための具体的な助言や勧告を行います。これにより、職場環境の安全と衛生が保たれます。
■ 衛生委員会への参画
常時50人以上の労働者を使用する事業場には、衛生委員会(または安全衛生委員会)の設置が義務付けられています。(※労働安全衛生法 第18条)
産業医は、この委員会の構成員として参画することが義務づけられています。
仮に名ばかり産業医で出席や内容確認、助言などを何もしていない状態であると、構成員として機能していると認められない場合があります。
- 専門的意見の提供:委員会の議題である労働者の健康障害の防止や健康保持増進に関する事項について、医学的な専門知識に基づいて意見を述べます。
- 審議への参加:事業場の健康管理計画や、特定の健康問題への対策など、重要な事項の審議に参加します。
- 情報共有:健康診断の結果や職場巡視で得られた情報などを委員会で共有し、議論を活性化させます。
■長時間労働者、高ストレス者との面談
法人は、特定の条件下にある労働者に対し医師による面談指導を行うことが義務付けられています。(※労働安全衛生法 第66条の八)
産業医でなくとも医師であれば面接が可能ですが、法人に産業医を置いている場合は通常、労働環境などを把握する産業医がこれを行います。
- 長時間労働者への面接指導:時間外・休日労働時間が一定の時間を超える労働者(具体的には、週40時間を超える労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる者など)から申し出があった場合、面接指導を行います。これは過労死などを未然に防ぐ上で極めて重要です。
- 高ストレス者への面接指導:ストレスチェック制度により、高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、面接指導を行います。精神面での健康問題の早期発見と対応に繋がります。
これらの面談を通じて、産業医は労働者の健康状態を詳細に把握し、必要な場合は休養や就業制限などの措置を事業者へ進言します。
■その他の法的業務
上記以外にも、産業医には労働安全衛生法で定められた様々な義務があります。(※労働安全衛生規則 第14条)
- 作業環境管理、作業管理の実施に対する助言:作業環境測定の結果に基づき、有害物質の管理や換気設備の改善などについて専門的な意見を述べます。
- 有害業務に従事する労働者の健康管理:特定の有害な業務(例:有機溶剤取扱業務、放射線業務など)に従事する労働者に対して、特別の健康管理措置について助言します。
- 健康教育、健康相談、その他の健康保持増進措置:労働者に対する健康に関する情報提供や相談対応も、産業医の重要な義務の一部です。
- 労働者の健康に関する情報の記録と管理:労働者の健康診断結果や面談記録など、個人の健康に関する重要な情報を適切に記録し、秘密保持に努めながら管理します。
- 疾病の診断、治療に関する指示:産業医は治療を行う医師ではありませんが、労働者の疾病に関して、適切な医療機関の受診勧奨や、症状に応じた就業上の配慮について助言することがあります。
産業医の業務内容(義務ではないが重要な業務)
ここからは、労働安全衛生法で明確に義務とは定められていないものの、企業の健康経営や生産性向上に貢献するために、多くの産業医が行う重要な業務について解説します。
■労働災害防止のための助言
産業医は、労働者の健康面から労働災害を未然に防ぐための助言を行います。
これは、職場巡視や健康診断の結果などを踏まえ、潜在的なリスクを発見し、具体的な対策を提言するものです。
例えば、特定の作業における姿勢の改善、安全靴の着用指導、適切な休憩の取り方など、多岐にわたります。
これは直接的な法的義務ではありませんが、労働者への安全配慮義務として極めて重要な医師の意見となります。
■休職・復職判定への助言
労働者が疾病やケガで休職する際、また休職から復職する際に、産業医は医学的な見地から事業者へ助言を行います。
- 休職の必要性・期間の判断:主治医の診断書や労働者の状態を踏まえ、休職の妥当性や適切な休職期間について意見を述べます。
- 復職の可否・時期の判断:復職に際しては、労働者の健康状態が職務遂行に耐えうるか、元の職場への復帰が可能か、段階的な復帰(試し出勤など)が必要かなどについて判断し、事業者に具体的な意見を伝えます。
- 復職後のフォローアップ:復職後の労働者の健康状態を定期的に確認し、必要に応じて就業上の配慮の継続や変更を助言します。
この助言は、労働者の円滑な社会復帰を支援し、再発防止に繋がるだけでなく、企業の休職・復職制度の適切な運用にも寄与します。
■メンタルヘルス対策
近年、メンタルヘルス不調は労働者の健康問題の中でも特に増加傾向にあります。産業医は、メンタルヘルス対策において中心的な役割を担います。
- メンタルヘルスに関する相談対応:労働者からのメンタルヘルスに関する相談に応じ、適切なアドバイスや医療機関への受診勧奨を行います。
- 職場環境改善への助言:ストレスの原因となりうる職場環境の要因(人間関係、業務量、ハラスメントなど)について、改善策を事業者に提案します。
- 管理監督者への教育・研修:管理監督者が労働者のメンタルヘルス不調のサインに気づき、適切に対応できるよう、研修などを行います。
- 緊急時の対応:自殺リスクのある労働者など、緊急性の高いケースにおいては、関係者と連携し、迅速な対応を支援します。
これらの活動は、法的義務であるストレスチェックや高ストレス者面談を補完し、より包括的なメンタルヘルスケア体制を構築します。
■労働者への健康教育
産業医は、労働者全体の健康リテラシー向上を目的とした健康教育も行います。
- 健康に関する講演や研修:生活習慣病予防、メンタルヘルスケア、感染症予防など、様々なテーマで講演や研修を実施します。
- 健康情報の提供:健康に関するパンフレットの監修や、社内報での情報発信などを通じて、労働者が自ら健康を管理するための知識を提供します。
これらの活動を通じて、労働者一人ひとりが健康意識を高め、自律的な健康管理を実践できるよう促します。
企業が注意すべき産業医関連の法令と罰則
産業医を選任し、その業務を適切に遂行してもらうためには、企業側が関連する法令を正確に理解し、遵守することが不可欠です。
■産業医の選任条件と手続き
前述の通り、常時50人以上の労働者を使用する事業場では産業医の選任が義務です。選任後14日以内に、所轄の労働基準監督署長に「産業医選任報告書」を提出する必要があります。(※労働安全衛生規則 第13条第2項)
■関連法令と法改正リスク
産業医の業務は、主に労働安全衛生法に基づいています。特に、労働安全衛生規則に定められた「産業医の職務」は、企業が産業医に依頼すべき具体的な業務内容を示すものなので、定期的に確認することが重要です。
労働安全衛生法は、社会情勢の変化や新たな健康問題の発生に対応するため、定期的に改正が行われます。例えば、ストレスチェック制度の導入や、長時間労働者への面接指導の強化などは、近年の法令改正によって義務化されたものです。
企業は、最新の法令情報を常に把握し、規則の変更に迅速に対応する義務があります。企業と産業医が連携して情報収集を行うことが重要です。
■産業医の資格要件
産業医として選任できる医師には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。(※労働安全衛生規則 第14条第2項)
- 厚生労働大臣が指定した法人で産業医研修を修了した者
- 産業医の養成を目的とする正規の大学で指定の過程を修め卒業し、実習を履修した者
- 労働衛生コンサルタント試験に合格し、その試験区分が保健衛生である者
- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、講師の経験者
- その他、厚生労働大臣が定める者
これらの要件を満たさない医師は、産業医として選任することはできません。誤って資格のない医師を選任してしまうと、法令違反となります。
■産業医を選任しなかった場合の罰則とリスク
常時50人以上の労働者を使用する事業場で、産業医を選任しなかった場合、労働安全衛生法に基づき罰則が発生する可能性があります。(※労働安全衛生法 第120条第1号)
罰則だけでなく、産業医を選任しないことには以下のようなリスクが伴います。
- 労働者の健康リスクの増大:健康問題の早期発見・対応が遅れ、疾病が悪化したり、メンタルヘルス不調が深刻化したりするリスクが高まります。
- 労働災害のリスク増大:職場環境の不備や作業上のリスクが見過ごされ、労働災害が発生する可能性が高まります。
- 企業の社会的信用の失墜:法令遵守意識の低い企業として、企業イメージが損なわれる可能性があります。
- 訴訟リスクの増大:労働者の健康問題が悪化し、企業側の責任が問われる訴訟に発展するリスクがあります。
これらのリスクを避けるためにも、産業医の選任義務は確実に履行し、適切な産業医を選任することが重要です。
義務を遂行できる「良い産業医」の選び方と注意点

産業医の選任は単なる義務の履行に留まらず、企業の健康経営や労働者のパフォーマンスを支えるための投資とも言えます。
しかし、産業医も人材のひとりであり、その専門性や対応力は様々です。義務を確実に遂行し、さらに企業のニーズに応えられる「良い産業医」を選ぶためのポイントと注意点を見ていきましょう。
関連記事・・・産業医の選任に必要な費用感・契約形態とは?
■信頼できる産業医を見極めるためのポイント
単に法令を遵守するだけでなく、企業の状況や文化を理解し、健康経営に貢献しようとする産業医を見極めましょう。
- 労働衛生に関する知識と経験: 産業保健に関する専門知識はもちろん、労働環境や労働にまつわるリスクについての理解があるか。
- メンタルへルス・フィジカルヘルスへの対応:産業医として心身どちらの健康課題にも対応する姿勢があるか。
- コミュニケーション能力: 経営層、管理職、労働者それぞれと円滑なコミュニケーションが取れるか。特に労働者の話を傾聴し、信頼関係を築けるか。
- フットワークの軽さ: 必要に応じて柔軟に対応してくれるか、定期的な職場巡視をきちんと行ってくれるか。
- 企業への理解や貢献に対する姿勢: 自社の事業内容や企業文化に興味を持ち、健康課題を通じて企業に貢献しようとする姿勢があるか。
これらの特徴を持つ産業医は、信頼できる企業のパートナーとなるでしょう。
■産業医の実績や推薦状
候補となる産業医の選定にあたっては、その実績や専門分野を確認しましょう。
- これまでの経験: どのような業種や規模の企業で産業医を務めてきたか。
- 得意分野: メンタルヘルス、生活習慣病、特定有害業務など、得意とする専門分野は何か。
- 推薦状や紹介者の評価: 可能であれば、推薦状や、紹介者からの評価を聞くことで、客観的な情報を得ることができます。
■産業医選びの具体的プロセスと期間
産業医を選任する上で「急いで選任しなければ」「義務だから仕方なく」といった考えで短期間に選任を進めてしまうと、法的義務対応が満足にできず、結果として産業医の変更が必要になるケースも少なくありません。
希望のタイミングで選任をスタートするためには、契約において数ヶ月程度の期間を見ておくことが重要です。以下のような点を考慮し、計画的に選任を進めましょう。
具体的な産業医選びのプロセスは以下のようになります。

- ニーズの明確化(目安:1~2週間):
- 自社が抱える健康課題(例:メンタルヘルス不調者の増加、長時間労働者の多さなど)を把握する。
- 産業医に求める役割や専門分野(例:メンタルヘルスに強い、特定有害業務の経験があるなど)を明確にする。
- 来社頻度や対応方法(オンライン対応の可否など)の希望を整理する。
- 候補者の情報収集(目安:2週間~1ヶ月):
- 産業保健総合支援センター、医師会、産業医紹介サービス、既存の取引先からの紹介など、多様なルートで候補者を探す。
- 候補者のプロフィールや実績を確認する。
- 候補者との面談を設定し、直接会って人柄やコミュニケーション能力、企業への理解度などを確認する。
- 具体的な業務内容や報酬、契約条件について細かくヒアリングする。この際、前述した「法的義務」と「通常業務」について、どこまで対応可能かを確認しましょう。
- 選定・契約(目安:2週間~1ヶ月):
- 自社のニーズに最も合致する産業医を選定し、契約を締結する。
- 契約内容には、業務範囲、報酬、契約期間、守秘義務、解約条件などを明記する。
- 労働基準監督署への届出(14日以内):
- 産業医選任後14日以内に、所轄の労働基準監督署長に「産業医選任報告書」を提出する。
この一連のプロセスには、ある程度の期間を要することを想定しておきましょう。もちろんこれより短い期間での選任も可能ですが、初めて産業医を選任する企業は、とくに余裕のあるスケジュールが確保できることが望ましいです。
■選任前の対応業務確認
産業医の目星がついたら、選任前に法人として希望する対応業務にかかわる確認をしておくとスムーズな導入が可能になります。
- 企業情報の共有: 業務の優先順位などの参考になるよう、企業の状況(訪問場所、組織体制、就業規則など)や、従業員の健康状態に関する情報を共有します。
- 業務環境の確認: 業務遂行にかかわる個人情報の共有方法や環境(面談場所の提供など)、該当部門の組織体制の確認をしておく必要があります。
- 業務方針のすり合わせ: 産業医の職務範囲や業務頻度について、事業者側と産業医側で認識のずれがないよう、すり合わせを行いましょう。特に、法的義務ではない「通常業務」についても、どこまでを依頼するのか、優先順位も含めて事前に合意形成しておくことが大切です。
まとめ:適切な産業医選任で企業と従業員の健康を守る
本記事では、企業の担当者が知るべき産業医制度の法的義務と、義務ではないが重要な役割について詳しく解説しました。
産業医の選任や業務については、怠ると労働基準監督署の指導や罰則の対象となります。
また、従業員の心身の健康維持は、企業の人材確保や生産性向上にもつながりますので、ぜひしっかりとした「良い産業医」を選任しましょう。
■対応業務で不安なことは労働基準監督署へ確認を
産業医の業務内容や選任に関する法令、または個別の事例について判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署に相談することをおすすめします。
労働基準監督署は、労働安全衛生法に関する専門的なアドバイスを提供してくれる公的機関であり、正確な情報を得ることができます。
■産業医選任は信頼できる人物や団体からの紹介もおすすめ
適切な産業医を見つけるのは、一朝一夕には難しい場合があります。
特に、自社に最適な産業医を探す際には、信頼できる産業保健の専門家や、産業医紹介の実績がある団体からの紹介も有効な手段です。
関連サービス・・・産業医の選任で悩んだらこちら『ウェルビーイングをともに。産業医With』
お役立ち資料
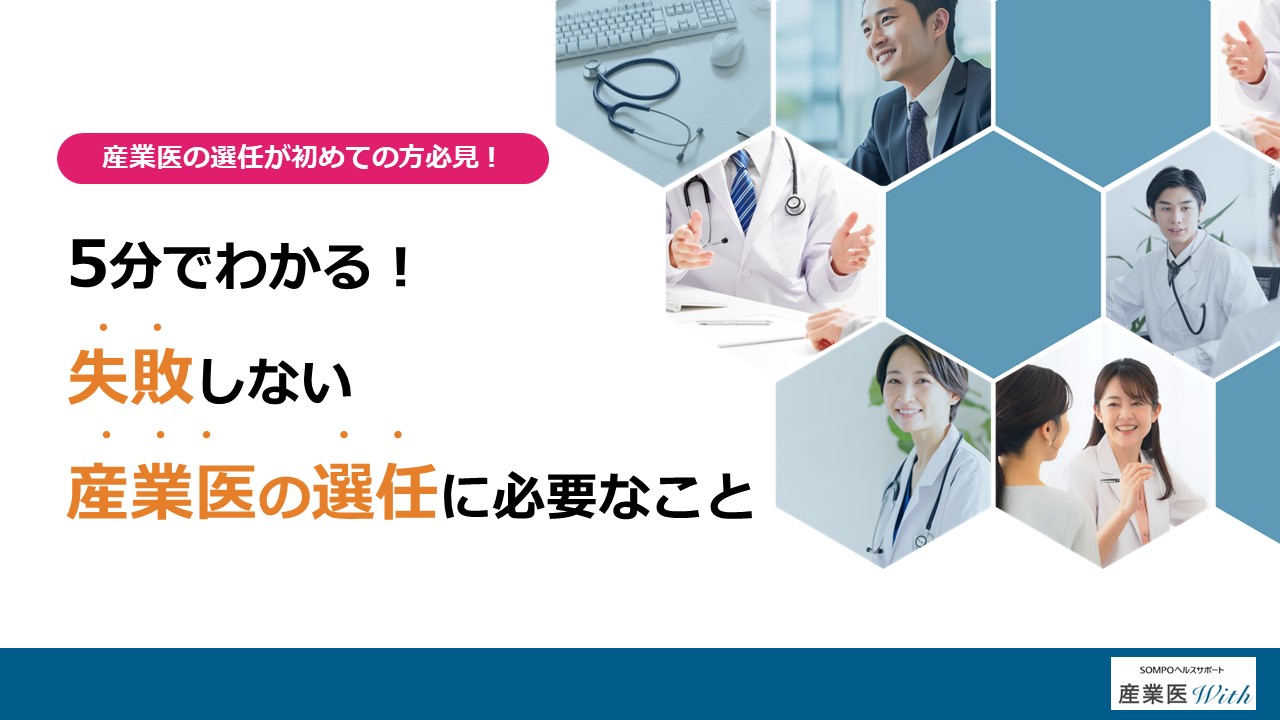 ■5分でわかる!失敗しない産業医選定に必要なこと
■5分でわかる!失敗しない産業医選定に必要なこと
産業医の選任で注意すべきポイントや知っておくべき情報を
”失敗しない”観点からまとめています。
