UP
健康経営度調査に取り組むべき理由とは?調査票のメリットを解説
目次
【お役立ち資料】
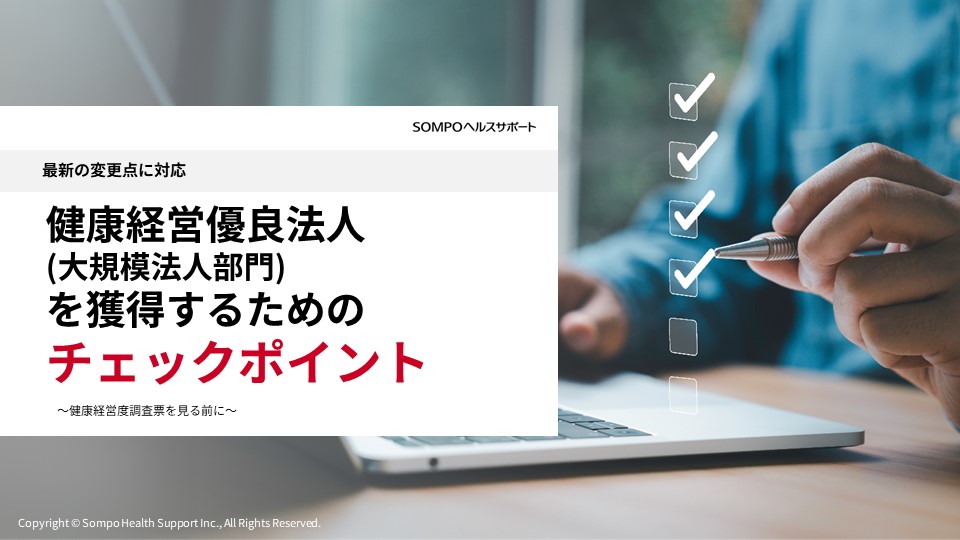 健康経営優良法人を獲得するためのチェックポイント
健康経営優良法人を獲得するためのチェックポイント
健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定を目指す企業が、
どのような基準を満たすべきかを整理し、
スムーズに申請を進めるためのガイドです。
健康経営度調査に取り組むべき理由とは?調査票のメリットを解説

健康経営に高い関心が寄せられている中、経済産業省が実施する「健康経営度調査」の重要性が注目されています。経営規模を問わず、どのような企業でも健康経営度調査を取り入れることは、大きなメリットがあるでしょう。
本記事では、企業が健康経営度調査に参加する意義や、調査票に取り組むメリット、具体的な内容について詳しく解説します。企業経営層の方や人事労務の担当者は、健康経営度調査についての理解を進めていきましょう。
*「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
■健康経営度調査とは
健康経営度調査は、経済産業省が主に大規模企業を対象に毎年実施している調査です。この調査は、企業の健康経営への対応状況を含めて評価するものであり、「健康経営銘柄」の選定や「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定に活用されています。
調査票は多岐にわたる項目で構成され、企業の健康経営に関する方針、体制、具体的な解決、評価・改善の取り組みを詳細に問うものとなっています。健康経営の現状を客観的に把握し、改善点を見いだすことができる調査です。
また、健康経営度調査は、専門家による委員会で策定されています。健康経営の進め方がわからない企業にとって、健康経営度調査に参加することで健康経営のために必要な取り組み内容が理解できるでしょう。
【関連記事】健康経営優良法人になるとどうなる?制度の内容とメリットを簡単に解説
■健康経営度調査を行う目的
健康経営度調査の主な目的は、法人の健康経営の困難状況とその経年変化を分析することです。また、「健康経営銘柄」の選定および「健康経営優良法人(規模法人部門)」の認定のための基礎情報を得ることも重要な目的の1つです。
大企業や中小企業の健康経営の取り組み状況を分析することは、企業側においても大きなメリットがあります。たとえば、調査を実施した企業に対しては、専門家からフィードバックがあるため、客観的な視点で健康経営の状況を把握できるのです。
このように、健康経営度調査では、経済産業省が日本企業全体の健康経営の取り組みを把握し、政策立案や支援策の検討に活用しています。
■中小企業も取り組むべき理由
健康経営度調査は、大規模企業を主な対象としていますが、中小企業にとっても大きな意義があります。大規模か中小かに限らず、企業が健康経営度調査を取り入れる意味は、健康経営や優良法人認定のポイントを理解するのに有効だからです。また、健康経営優良法人認定の基準を知ることができれば、自社の取り組みの方向性を決める際にも役立ちます。
従業員の健康増進と企業価値の向上につながる具体的な取り組みを学べ、結果として企業の持続的な成長につながることが期待できます。
取り組むメリット

健康経営度調査に取り組むことは、健康経営に取り組みたい企業にとってもさまざまなメリットを得られます。以下が主に3つのメリットです。
- 健康経営の取り組みの理解が深まる
- 取り組みの効果がわかる
- 自社の現況・課題を客観的に評価できる
それぞれのメリットについて、具体的に詳しく見ていきましょう。
■健康経営の取り組みの理解が深まる
健康経営の取り組みを始めたばかりの企業や、何から始めればよいかわからない企業にとって、健康経営度調査票に回答することは非常に有効です。調査票の質問項目から、健康経営に必要な要素や重要な点を理解できます。
たとえば、経営理念の健康経営への組み込み方、体制組織の整備、具体的な実践の方法など、健康経営を推進する上で必要な要素を学べるでしょう。また、自社の健康経営の方向性を決める際の指針にもなります。
■取り組みの効果がわかる
健康経営度調査に毎年回答することで、自社が抱える健康経営課題の経年変化を把握できます。調査の回答によって、取り組みの効果を客観的に評価し、改善点を見つけられるでしょう。
たとえば、従業員の健康状態の変化や生産性の向上、離職率の低下など、さまざまな指標の推移を追跡することで、健康経営の取り組みが実際にどのような成果をもたらすかを確認できます。
これらの情報は、今後の健康経営戦略を進める上での引き出しとなり、経営層への報告の際にも非常に有用です。
■自社の現況・課題を客観的に評価できる
健康経営度調査の結果は、全国の企業を対象とする集計データとして公開されます。これにより、自社の健康経営の状況が、同業他社や全国平均と比較してどの程度のレベルなのかを客観的に評価できます。
この比較を通して、自社の強み・弱みを明確に把握し、重点的に取り組むべき課題を特定できます。また、競合の優れた取り組みを参考にすることで、自社の健康経営をさらに発展させられるでしょう。
質問される5つの評価項目

健康経営度調査票は、企業の健康経営の取り組みを含めて評価するために、専門家による判定基準として、以下の5つの大項目に分けて質問が設定されています。
(1)経営理念・方針
(2)組織体制(経営基礎)
(3)制度・施策実行
(4)評価・改善
(5)法令遵守・リスクマネジメント
各項目について、具体的な内容を見ていきましょう。
(1)経営理念・方針
まず、企業の経営理念や方針に、健康経営がどの程度左右されるかが評価されます。具体的には、以下のような点が問われます。
- 健康経営の推進に関する経営トップのコミットメント
- 取り組み方針の明文化や情報の開示状況
- 従業員パフォーマンス指標および測定方法の開示
たとえば、「健康経営の推進に関する方針を社内外に明文化し公表しているか」という内容の質問が含まれています。これは、健康経営の方針を社内外に発信しているか、従業員のパフォーマンス指標および測定方法を開示しているかを評価する質問です。
企業が健康経営をどの程度重要視し、組織全体に浸透されているのかを評価します。
【関連記事】 健康経営に欠かせない戦略マップとは? 企業が押さえるべき基本ポイント
(2)組織体制(経営基礎)
この項目では、健康経営を推進するための組織体制が整備されているかが評価されます。毎年調査票に回答すると、経年的に自社の変化が見えるので、取り組みの成果を評価しやすくなります。
具体的には、以下のような点が問われます。
- 健康経営の実施体制(責任者や専門家の配備など)
- 産業医や保健師などの専門職の関与状況
- 健保組合等保険者との協議・連携
たとえば、「健康経営の推進にあたり、専門職(産業医、保健師等)はどのように関与しているか」といった内容の質問が含まれています。これらの質問によって、健康経営を効果的に推進するための体制が最適であるかが評価されます。
(3)制度・施策実行
この項目は、健康増進に向けた施策のバランス、健診結果に基づく健康経営の施策立案、健康保持・増進に向けた教育など、具体的な健康経営の当面の実施状況を評価するものです。5つの項目の中で最も設問数が多く、さらに以下のような3つの中項目に分かれています。
①従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討
②健康経営の実践に向けた土台づくり
③従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策
それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
①従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討
この中項目では、従業員の健康状態の把握方法と対策を評価します。健康診断の実施頻度や受診率、ストレスチェックの実施など、健康経営の基礎となる健診・検診等の活用・推進状況についての質問です。
②健康経営の実践に向けた土台づくり
この中項目では、健康経営を効果的に実践するための組織の基盤の整備状況について質問されます。フレックスタイム制やテレワークなど柔軟な働き方の導入状況が問われ、ワークライフバランスの推進に向けた取り組みができていることが評価項目です。
また、ヘルスリテラシーの向上として、健康経営に関する従業員教育の実施状況なども評価の対象となります。
③従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策
この中項目では、従業員における心身の健康促進に向けた具体的な取り組み実施状況を評価します。運動促進プログラムや社内スポーツイベントの開催、健康的な食事の提供、禁煙支援プログラムの実施などが評価項目です。
また、メンタルヘルス対策として、ストレスマネジメント研修の実施や相談窓口の設置、復職支援プログラムの整備状況なども調査項目に含まれます。
(4)評価・改善
この項目では、定期的な評価を通じて健康経営の取り組みの効果や成果を検証し、次のステップや改善点を発見できるか、施策全体の評価ができているのかを判定します。主な評価項目は、以下のとおりです。
- 健康経営の取り組みによる効果の測定方法
- 健康経営の取り組みに関する従業員満足度
- 評価結果に基づく改善策の実施状況
たとえば、「健康経営の取り組みによる効果を測定しているか」といった内容の質問が含まれています。
これらの質問では、PDCAサイクルを回しながら健康経営を継続的に改善する体制が整っているかを評価します。
(5)法令遵守・リスクマネジメント
この項目では、健康経営に関連する法令の遵守状況や、健康関連のリスクマネジメントの管理体制を評価します。主な評価項目は、以下のとおりです。
- 労働基準法または労働安全衛生法等の遵守状況
- 定期健康診断の実施と結果の通知状況
- 感染症対策や災害時対応体制
- 50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施状況
たとえば、「従業員の健康管理に関連する法令について、遵守するための仕組みを定めているか」といった内容の質問が含まれています。労働基準法または労働安全衛生法の遵守、リスク管理を適切に行っているかを評価する項目です。
回答の流れ

健康経営度調査票に回答する際は、専用サイトにて申請をする必要があります。具体的な流れは、以下の5ステップです。
1.専用サイトのIDを発行する
2.健康経営度調査票を取得する
3.健康経営度調査票に回答する
4.後日届いたフィードバックを確認する
5.健康経営優良法人の認定スケジュール
1つずつ、具体的に流れを見ていきましょう。
■専用サイトのIDを発行する
健康経営度調査票に初めて回答する場合、まずは専用サイト「ACTION!健康経営」にアクセスし、「新規ID発行」から企業IDを取得します。過去に回答したことがある企業には、調査票の受付開始時に電子メールでご案内が送られます。
このIDは企業ごとに固有のものが当てられ、毎年の回答や過去のデータの参照に使用されます。ID発行の際には、企業の基本情報や担当者の連絡先の入力が必要です。
よって、IDは厳重に管理し、担当者の変更時は速やかに更新することが望ましいでしょう。また、複数の部署が協力して回答する場合は、社内でIDの共有方法を決めておくと安心です。
■健康経営度調査票を取得する
健康経営度調査票の取得・申請は、専用の特設サイト「ACTION!健康経営」から行います。サイトにログインし、「健康経営度調査」のセクションから最新の調査票をダウンロードしましょう。
調査票はExcelファイル形式で提供されており、オンラインで直接入力することも可能です。調査票には、回答の手引きや用語の説明なども含まれているため、それらを参照しながら回答を進めます。
取得した調査票は社内の各部署などで共有し、必要なデータや情報を収集する準備を始めます。また、過去の回答内容も参照できるため、経年変化も確認しながら進めると効果的です。
■健康経営度調査票に回答する
ダウンロードした調査票に、必要事項を入力します。回答には企業の健康経営に関するさまざまなデータや情報が必要となるため、人事部門や健康管理部門など、関連部門と協力して回答を作成します。各部門間の協力は回答の精度を高めるために有効です。各部門からの情報を統合し、整合性を慎重に確認しましょう。
回答完了後は、専用サイトに電子データでアップロードします。回答期間は、通常8月から10月頃までですが、具体的な期限は毎年公開される案内で確認してください。余裕をもって回答を完了させ、回答に誤りがないかを確認するためにも、提出前に複数人でチェックすることが大切です。
■後日届いたフィードバックを確認する
調査票の回答後、大規模法人部門にて回答した法人と、健康経営優良法人(中小規模法人)ブライト500に申請した法人にはフィードバックシートが送付されます。また、申請したすべての法人に評価結果が送られます。公開されている集計結果と共に、自社の評価を確認しましょう。
フィードバックシートには、自社の回答結果と全体の平均値の比較、各項目の得点などが記載されています。公開されている集計結果とあわせて確認することで、自社の健康経営の状況を客観的に評価し、今後の改善点を見いだせます。
経営層や関連部門と共有し、次年度の健康経営戦略に活用することが重要です。
■健康経営優良法人の認定スケジュール
健康経営度調査は、健康経営的優良法人の認定過程の一部として実施されます。例年のスケジュールは以下のとおりです。まずは、8月~10月の間に、健康経営度調査の実施企業は「ACTION!健康経営」サイト調査票に回答します。この期間中、通常は自社の健康経営の取り組みを詳細に報告します。
11月〜1月は審査期間であり、提出された調査票を基に、日本健康会議認定事務局が厳正な審査を行います。この間、必要に応じて追加資料の提出を求められることもあります。
2月頃には認定結果の通知審査結果が各申請企業に通知、3月に健康経営優良法人の発表認定企業のリストが公式に発表されます。
企業は、このスケジュールを念頭に置き、計画的に健康経営の取り組みを進め、調査に備えましょう。また、認定後も継続的な改善が求められるため、調査結果を次年度に反映させることが大切です。
調査票の設問内容は毎年変わる|令和6年度の追加項目

健康経営度調査票の設問内容は、社会情勢と健康経営の動きにあわせて毎年更新されるため、その年の変更内容をチェックする必要があります。令和6年度は、健康経営度調査の以下の3つの柱について方向性が示されました。
- 健康経営の可視化と質の向上
- 新たなマーケットの創出
- 健康経営の社会への浸透と定着
調査票では、経営層の関与強化、データ活用の促進、多様な従業員への健康支援など、重要な改定が行われました。健康経営の担当者は、設問内容を確認し、自社の健康戦略経営に反映させることが求められます。
■健康経営推進の専門職の実施範囲
令和6年度の健康経営度調査票では、産業医や保健師の健康経営への関与状況について、より詳細な評価が行われるようになりました。とくに、産業医や保健師の健康経営について「施策の実施」範囲での関与状況が新たに問われ、専門職の役割がより重視されています。
専門職の配置と整備は、健康経営の質の向上を目指すために当然の動きであり、専門職の知見を踏まえた実践的な取り組みが期待されています。
企業は、産業医や保健師との連携を強化して専門知識を現場に反映させ、健康管理における対策の検討から実施、評価まで幅広く専門職を活用することが求められています。
■40歳未満の従業員の健康診断データ提供が評価対象に
令和6年度の調査票では、【Q30】(b)で問われる40歳未満の従業員に関する健康診断データの提供状況が評価対象項目となりました。令和5年度版で記載されていた「◆今年度、当設問は一切評価に使用しません。」の記述がカットされています。
これは、一次予防を促進するためです。企業は、全年齢層の従業員の健康データを正しく管理し、活用することが求められています。
なお、40歳未満の従業員の健康データ提供には、本人の同意が必要な場合があるため、個人情報保護の観点から慎重な対応が必要です。保険組合との連携を強化し、若年層の健康管理を効果的に進めることが求められるでしょう。
■PHRの活用促進のための環境整備状況(新設)
令和6年度の調査票では、PHR(パーソナルヘルスレコード)の活用促進に関する設問【Q43】が新たに追加されました。従業員が自身のPHRを活用できる環境が整っているか、その整備状況が問われています。
PHRの活用は、個人の健康管理能力の向上につながるために、企業はPHR活用のための環境整備を進めることが求められています。
具体的には、従業員が自身の健康データを容易に閲覧・管理できるシステムの導入や、PHRを活用した健康指導プログラムの実施などが挙げられるでしょう。健康状態の管理や閲覧、健康モニタリングなど、従業員の健康増進に役立てるためにも、PHRの活用を積極的に推進することが期待されています。
健康経営度調査に参加し、自社の健康経営施策を加速
健康経営度調査は、企業の健康経営を評価し改善につなげる重要なツールです。中小企業を含むすべての企業にとって、調査参加の意義とメリットがあります。とくに中小企業には、健康経営の実践方法を学び、従業員の健康と企業の価値向上を同時に実現する企業体制をつくる良い機会となるでしょう。
ただし、調査の効果的な活用には専門知識が必要です。専門家のサポートを活用することで、より効果的な健康経営の実践が可能になります。
SOMPOヘルスサポートの「健康経営推進支援」では、経験豊富なコンサルタントが、企業の健康経営づくりを伴走型で支援します。現状把握からのコンセプトづくりに始まり、目標とそのためのKPI設定まで支援します。
健康経営度調査についてお悩みの企業は、ぜひ、こちらのページからご相談ください!

