UP
エンゲージメントサーベイとは?ストレスチェックとの違いや導入ポイント
目次
エンゲージメントサーベイとは?ストレスチェックとの違いや導入ポイント

ストレスチェックは多くの企業で実施がされている施策です。最近では、従業員50名未満の事業所に対しても実施を義務付ける法案が検討されています。
一方で、エンゲージメントサーベイに関しては法的な規定もなく実施の有無は各企業の判断に委ねられていますが、これからエンゲージメントサーベイの導入を検討している企業の中には、既に行っているストレスチェックとのすみ分けや違いについて判断に迷うケースも多いのではないでしょうか。
今回の記事では、エンゲージメントサーベイとストレスチェックの使い分けについて解説します。
エンゲージメントサーベイとは?
エンゲージメントサーベイは、従業員のエンゲージメント(会社、組織、仕事などへのポジティブな関与、モチベーション、愛着心)などを可視化するツールです。
これにより、企業は従業員のエンゲージメントレベルを把握し、職場環境や組織文化の改善のための具体的な施策を立案することができます。エンゲージメントサーベイを通じて得られるデータは、企業の人材戦略・育成において非常に重要な役割を果たします。
また、従業員が仕事に対してどのような感情を抱いているのかを理解することで、会社側はより適切な支援策や対策を検討し、職場環境を改善することができます。
【特徴面】ストレスチェックとの違い
ストレスチェックは、主に従業員の心身の状態を測定するために用いられます。精神的なストレスの有無や程度を把握し、必要に応じてフォローアップを行うことを目的としています。ストレスチェックは心身の健康面にフォーカスしているのに対し、エンゲージメントサーベイは仕事や組織に対するポジティブな気持ちにフォーカスしていますので、両者を併用することで、より包括的な従業員支援の体制を築くことができます。
また、ストレスチェックは法的に決められた方法に沿って実施することで、高ストレス者と呼ばれる従業員に対して医師面接勧奨といった直接的なアプローチを行うことができます。
対してエンゲージメントサーベイは、ストレスチェックのように個別の従業員にアプローチをするというよりは、会社、組織といった単位での状況を把握し、集団に対してアプローチをするためのものとなります。この両者の違いを理解し、適切に使い分けることが重要です。
効果的な利用方法とは?

それぞれの特徴の違いを知ったうえで、次は利用方法においての両者の違いをみていきましょう。
【活用面】ストレスチェックとの違い
ストレスチェックはリスクマネジメント観点から利用されることが多く、問題の早期発見と対応に向いています。言い換えますとマイナス面をゼロにする観点で利用されれることが多いです。エンゲージメントサーベイは組織課題の発見もそうですが、強みをより伸ばす面でも利用されます。
こちらはゼロをプラスにする観点で利用されることが多いです。厳密には、ストレスチェックでも強みが見い出せたりエンゲージメントサーベイでも課題面が見い出せますので、明確な線引きはありませんが、このように捉えていたければ分かりやすいでしょう。
このように、両者の守備範囲は重ならない点が多く、両者ともに導入している企業も増加しています。
エンゲージメントサーベイ導入前に注意すべきこと
エンゲージメントサーベイは十分利用に値するツールですが、導入前に必ず検討しておかなくてはならないポイントがあります。
目的を明確にする
サーベイ活用の目的をあらかじめ設定しておくことが重要です。生産性を上げるために従業員の主体性や自律性を把握する、退職者を減らすために会社に対する帰属意識や業務に対する肯定的な感情度合いを把握する、などです。
少し調べていただければわかりますが、エンゲージメントサーベイは種類も多く、特徴も変わってきます。従業員のエンゲージメントを可視化することで何をしたいのかを明確にしておきましょう。
従業員の理解
従業員の理解を得ないまま実施することで、サーベイ実施に否定的になり正確な回答を得られない可能性があります。
また、回答そのものを拒否する場合もあるでしょう。こうした事態を防ぐために「従業員エンゲージメントがなぜ重要なのか」「なぜサーベイを実施するのか」を事前に周知することが重要です。
周知の方法としては、メールや社内SNSも有効ですが、初めはなるべく事前説明会などの形式で時間をとって説明することをお勧めします。オンラインでのミーティングも浸透しているため、時間の確保もそれほど難しくはないでしょう。
説明会を実施する際、盛り込んでいただきたい点があります。
1点目は「不利益にならないこと」を伝えましょう。
冒頭でも記載をしましたが、元々従業員エンゲージメントが低いと思われる会社の場合、会社側が良かれと思い実施することに対して従業員が無意識のうちにネガティブな解釈をしてしまうことがあります。
サーベイの結果を評価や査定に用いるなどの誤った解釈をされないように、従業員の不利益とならないことを伝えましょう。
2点目は「個人結果の取扱い範囲」を明確にしましょう。
サーベイの個人結果をみることができるのはどの部署のどの範囲までか、管理職・経営層は含まれるのか、など事前に明示しておくことです。明示しておくことは会社への信頼につながりますので、曖昧にはしないでおきましょう。
エンゲージメントサーベイを導入しなくても良いケース
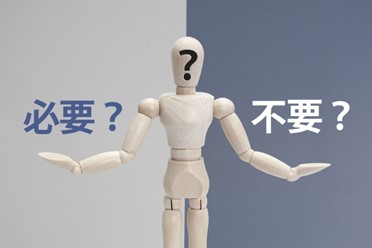
エンゲージメントサーベイは優れたツールですが、企業の状況によっては導入を見合わせたほうがよい場合があるかもしれません。
例えば企業において労働安全衛生上の問題が数多くある場合です。従業員の長時間残業が蔓延化している、業務上のストレスによるメンタルヘルス不調や休職が増加しているなどの場合、まずやるべきことはエンゲージメントの向上ではなく労働安全衛生法の遵守、リスクをはらんでいる職場環境の改善、休復職者への専門的な支援などです。こうした問題の解決なしに、エンゲージメントの向上は決して期待できないでしょう。
良いサーベイ(ベンダー)の見分け方
信頼できるベンダーを選ぶ際には、過去の導入実績や成功事例、提供しているサーベイそのものを確認することが重要ですが、それ以外に意外と盲点になりがちな点についてご説明します。それは、サーベイを提供しているベンダーの得意分野は何なのか、です。
あくまで印象値ですが、3種類のベンダーについてご紹介します。参考までに留めていただけると幸いです。
システム開発を生業としたベンダー
意外と多いのが、システム開発を生業としたベンダーです。外部の専門家の助言を得て、エンゲージメントサーベイを開発していることがあります。特徴としては機能を絞ったシンプルな設計のサーベイが多く、低価格な傾向があります。一方で、内部に専門家がおらず、サーベイ後のソリューション提案には弱いかもしれません。
HR系の課題解決が得意なベンダー
エンゲージメント関係に最も近しい領域のベンダーです。特徴としては組織開発コンサルタント、人材育成のプロなど内部に専門家を抱えていることが多く、専門性の高いサーベイを開発しています。手の込んだ作りをしている反面、価格は高めかもしれません。
メンタルヘルスケア領域に強いベンダー
エンゲージメントと比較的近しい領域であるメンタルヘルスケア領域で培ったノウハウをベースに、独自のエンゲージメントサーベイを開発しています。エンゲージメント単体の専門性はHR系には及ばないものの、ストレスチェックと合わせてエンゲージメントサーベイを実施できるなどの利便性を確保しているケースが多いです。
当社は、年間100万名以上のストレスチェック実績から、エンゲージメントサーベイ「A’Uno」を開発いたしました。ぜひこちらご覧ください。
以上のように、提供ベンダーの得意分野によって特徴も様々ですので、導入を検討される場合は複数資料を請求し、どれが自社にあっているか慎重に見極める必要があります。
効果的な実施時期は?
エンゲージメントサーベイの効果的な実施時期は、企業の状況により変わります。共通していえることは、年度初めなどの組織変更が行われた直後の実施は避けたほうが良い、という点です。組織変更のような大きな環境変化が起きると、従業員は新しい環境に適応するまで一定の時間が必要となります。
この間にエンゲージメントサーベイやストレスチェックなどを実施してしまうと、普段の様子とは異なる一時的な状態が結果に表れやすいため、なるべく避けるべきです。
一般的には、組織変更のような環境変化から2~3か月は様子を見て、その後にエンゲージメントサーベイを実施することで定着した状態としての結果をみることができます。
最近では、エンゲージメントとストレスの両方を測定できる統合型サーベイも存在します。これにより、一度のサーベイで包括的なデータが得られるため、従業員の負担も少なく、効率的な分析と対応が可能となります。
実施後に必要なアクションとは?

組織結果の扱いについて
出力された結果に対し、まずは運営チームが内容を正しく理解できるようにしておく必要があります。尺度やカテゴリの意味、数値の高低が何を意味するか、設問構成など基本的な知識を持っておくことで、展開後に質問を受けたとしても正しい情報を伝えることができます。
・経営層へのフィードバック
経営層に対しては、主に①会社全体の傾向、強み、課題 ②各部門の傾向、強み、課題といった流れで説明をしたほうが良いでしょう。
自社の規模が大きく、部門数が多岐にわたる場合は、特に良い傾向を示した部門と結果が良くなかった部門をピックアップして説明することで、無駄なくフィードバックができると思います。
また、特に初回の実施であれば提供ベンダーのオプションサービスなどを活用し、代わりに報告してもらうことで、読み解きポイントのコツなどを吸収することもできます。
なお経営層に説明する際は、社として今後の対策をどうするべきかについても意識をしておくとよいかと思います。
初回であれば実態調査自体を目的とし、次年度以降の傾向を見てから対策を打つ、などの事例も多くあります。
・管理職へのフィードバック
部門フィードバックの対象となるのは、部門長(部長、課長級)となります。現場において裁量権を持つ管理職に自部門の傾向をしっかりと理解してもらうことはとても重要です。なお、この後管理職からさらに従業員へフォードバックをしてもらうことを想定し、運営チームと同じように各尺度の意味や数値の高低が示すものなどについて正しい知識をお伝えすることも忘れないでください。
会社によっては、この管理職へのフィードバックを研修やワークショップの形でベンダーに依頼する場合もありますし、自社で独自に改善案の提出などを行う場合もあります。
・従業員へのフィードバック
従業員へのフィードバックは、規模が大きくなりますので各部門ごとに行ってもらうのが良いでしょう。この場合の注意点としては、会社として結果を伝えて終わりではなく、対策についても今後検討していくといった改善への姿勢を示すことが重要です。導入初回で今年度は対策を打つ計画でなくとも、次回以降は対策まで視野に入れた計画にする、など将来展望を伝えることです。
これにより、従業員の信頼を得ることができます。フィードバックは、従業員が自身の意見が尊重され、組織がその意見を真剣に受け止めていることを実感できる機会となります。
その後の対策について
フィードバック後には、検討された対策案に基づき、具体的な施策を実行に移すことが重要です。定期的な進捗確認や、必要に応じた計画の見直しを行うことで、持続的な改善が期待できます。
対策自体に時間がかかるものであれば、施策が進行中であることを従業員に伝え、彼らの意見を反映することで、より効果的な改善が可能となります。対策の内容もそうですが、対策を進めていること自体が重要院に伝わることで、エンゲージメント向上の一助となり得ます。
対策の結果について。短期的な結果を求めない
まとめ
ストレスチェック後の対応や健康経営の推進もそうですが、従業員エンゲージメントの向上も単年では効果が見えづらく、中長期的な視点を持って取り組むことが必要です。
サーベイ・対策といった一連の取り組みに対し経営層が過剰な期待を寄せるあまり、早急な効果を人事に求めてくることがあります。その結果、目に見える結果が得られずに単年での取組みに終わってしまうなどの事態を避けるために、経営層の理解をしっかりと得ておきましょう。
運営側の人事が余計なプレッシャーを感じないようにすることが、成功の秘訣です。特に初めてエンゲージメントサーベイの導入を検討されている企業は、ここまでのポイントを意識してみてください。

エンゲージメントサーベイは、従業員の会社や仕事への愛着・モチベーションを可視化し、組織改善や人材育成に役立てるための調査です。一方、ストレスチェックは心身の健康状態を把握する法定調査で、個人への医師面談勧奨など直接支援が可能です。
エンゲージメントサーベイは組織単位での分析を目的とし、ゼロからプラスへの改善を目指すのに対し、ストレスチェックはリスク対応に重きを置きます。導入時は目的や従業員の理解を明確にし、信頼できるベンダー選定や結果への正しい対応も重要です。

